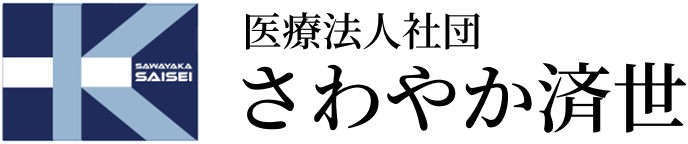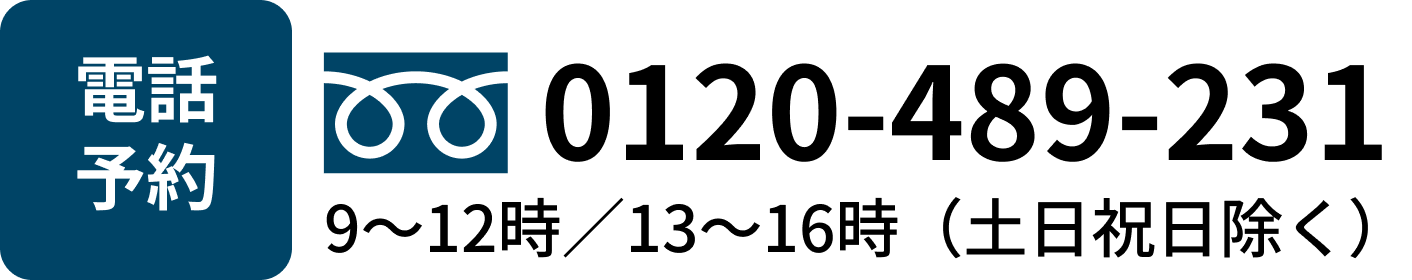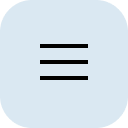ご予約およびお申込み時によくあるご質問
- 初めて当健診センターにて健康診断を受診するには?
-
すべて予約制となります。
ご予約の際は下記をご準備の上、電話にてご連絡または予約フォームよりお申込みください。- ① ご希望の健診コース
- ② 健康保険証の種類(健康保険組合名称 記号 番号)
- ③ 会社名
- ④ 郵便番号、住所、電話番号
※注意 当日受付は行っておりませんのであらかじめご了承ください人間ドック・健診のご予約
お申し込みはこちら - 初めて巡回健診車による健康診断を受診するには?
-
巡回健診については、付属施設の葛飾健診センターで承っております。
- ① ご希望の健診コース
- ② 健康保険証の種類(記号)
- ③ 大型観光バスが止められるぐらいの駐車場の有無
- ④ 20畳程度の部屋の有無が必要となります。
※当センターの担当者がご挨拶を兼ねて下見をさせていただく場合がございます。 - お申し込み方法は?
-
全国健康保険協会の場合
お電話またはメールフォームよりお問い合わせください。
健康保険組合の場合健康保険組合ごとに異なりますので、ご加入の健康保険組合のHPまたは直接ご確認ください。
健康診断についてよくあるご質問
- いつ頃、健康調査表(問診表)は届くのでしょうか?
-
基本的には、受診日の2~3週間前程度です。
- 健診は何時間くらいで終了しますか?
-
健診内容にもよりますが2時間~2時間30分程度 (当日結果説明含まず)
- いつ頃から、便は採ればよいのでしょうか?
-
健診日を含めて、6日間です。
- どうしても、便が1日分しか採れないのですが、どうしたらよいのでしょうか?
-
1日分だけでも、便を提出してください。
- 健診日の前日どうしても夕飯を8時までに済ませることができないのですが?
-
胃の中に食べ物が残っていると、胃部X線検査(バリウム検査)で精度に支障があります。また、他の検査にも影響が出る場合がございますので、出来る限りご案内の時間までに済ませてください。(最低、健診前10時間はあけてください。)
- 健診当日は、薬を飲んでもよいのでしょうか?
-
事前に主治医にご相談いただき、検査終了後に飲んでも問題がなければご持参ください。心臓病、高血圧の薬を服用されている方は、健診当日朝7時までに少量の水により服用してください。
- 妊娠中(の疑い)ですが、どのようにしたらよいのでしょうか?
-
必ず、受付時にお申し出ください。また、レントゲン検査を除き、ほとんどの検査項目がご受診できます。
- 生理中ですが、健診はできますか?
-
尿検査および子宮がん検査(子宮細胞診)を除き、ご受診できます。また、生理前に検便が採取できた場合は、受付をいたしますのでご提出ください。
- 生理が終わって5日目ですが、婦人科は受けられますか?
-
生理中、および生理後1週間は受診できません。
※生理後、1週間位経過してからの細胞がより良いとされており、より正確な検査結果がだせます。 - 心臓ペースメーカーを使用しておりますが、大丈夫でしょうか?
-
体脂肪測定は行えません。必ずスタッフにお申し出ください。
- いつ頃、健診結果は分かりますか?
-
- 人間ドック
- 当日8割程度の結果が出てそれに基づいて結果説明をしています。詳しい結果は3週間前後に郵送させていただきます。
- その他健診コース
- コースにより3週間前後でご自宅に郵送となります。
- クレジットカードは利用できますか?
-
NICOS、UC、UFJ Card、JCB、Diners Club International、Master card、VISA、DC,American Expressのいずれかがご利用になれます。
- 駐車場はありますか?
-
センターのとなりに5台分の専用駐車場がございますが、満車となった場合は近隣の有料パーキングをご利用いただくか、公共機関にてお越しいただきますようお願いいたします。
地図はアクセスをご参照ください。
【電車】
京成線立石駅より徒歩8分
【バス】
新小岩←→綾瀬・渋江公園前下車徒歩3分 - 事業所として受診します。負担金の会社請求はできますか?
-
月末締めで翌月下旬までにご請求書を送付致します。振込料はお客様ご負担でお願いしております。
乳がん健診について
- 超音波検査とマンモグラフィ、どちらを受ければよいでしょうか?
-
超音波検査、マンモグラフィは、それぞれに発見しやすいタイプの乳がんがあるので、2つの検査を併用することが理想です。どちらか一方のみでは発見されない場合もあります。日本人女性の乳がん罹患率のピークは40歳代です。また、血縁者に乳がん既往歴のある方、出産の経験がない方は2つの検査を併用することをおすすめします。
- どちらかにしたいのですが?
-
40歳未満の方には超音波検査、40歳から閉経前の50歳代の方には超音波検査とマンモグラフィを毎年交互に受けることをおすすめします。また、閉経後の50歳以上の方はマンモグラフィをおすすめします。
- どのくらいの頻度で受ければよいですか?
-
進行の早いがんの場合、2年に1度の検査では不十分です。年に1度、検査を受けることが理想的です。
- いつ検査を受ければよいですか?
-
閉経前の方は女性ホルモンの影響を受けますので、生理終了後の2~3日が最適といわれています。
- 乳腺症ってなんですか?
-
乳腺症は乳腺の生理的変化なので、痛みがひどくなければ治療の必要はありません。しかし、乳腺がしこり状に硬く触れるために、触診による診察だけでは、乳腺症かがんであるかを判断することが難しいケースもあります。したがって、月1回の自己触診(ご自身による乳房の視触診)と共に、年1回の検査(マンモグラフィまたは超音波検査。2つを同時にすることで、さらに精度は上がります)を受けることをおすすめします。
マンモグラフィについて
- マンモグラフィ(乳房撮影)って何?
-
乳房のX線写真のことです。
乳房はやわらかい組織でできているため、ふつうの胸部X線写真などとは違い、乳房専用のX線撮影装置を使って撮影します。 - どのようにして、検査(撮影)するのですか?
-
検査(撮影)は乳房を片方づつ、台とプラスチックの板で挟んで撮影いたします。また、この挟むことを圧迫といいます。上から下へ挟む方法(CC)と、斜めに挟む方法(MLO)の2種類があります。
- 痛いと聞いたのですが…。
-
乳腺を胸壁からなるべく離すために強く引っ張りながら押さえますので痛みを感じられる方もいらっしゃいます。特に、生理が始まる直前は女性ホルモンの影響で痛みを感じる場合もありますが、痛み方には個人差があり、リラックスをすることで少し改善できます。当センターでは、女性レントゲン技師が様子をみながら徐々に圧迫を行いますのでご安心ください。
- なぜ、圧迫するのですか?
-
この検査(撮影)は、1mmより小さい病気を見つけるものです。しっかりと“圧迫”をすることでよりよい検査ができ、X線の被ばく量が少なくなります。よりよいマンモグラフィの検査をするには、“圧迫”は必要ですのでご協力をお願いいたします。
- 胸部(X線)の検査をしたばかりですが…。
-
私たちは普段の生活しているなかで大気中などから自然放射線を意識せずに浴びています。年間一人あたりの線量は平均で2.4ミリシーベルトと報告されています。マンモグラフィで受ける乳房の被ばくは、日本人の平均的な乳房で一回の撮影で0.065ミリシーベルトです。胸部X線撮影では0.02ミリシーベルトです。X線検査ですので少しは被ばくを伴いますが、乳房だけという部分的なものなので特に問題はありません。またこの検査によって何か影響がでるという値ではありませんので心配はありません。安心して検査をお受けください。
乳腺超音波検診について
- 乳腺超音波検査では何がわかるのですか?
-
乳腺症は乳腺の生理的変化なので、痛みがひどくなければ治療の必要はありません。しかし、乳腺がしこり状に硬く触れるために、触診による診察だけでは、乳腺症かがんであるかを判断することが難しいケースもあります。したがって、月1回の自己触診(ご自身による乳房の視触診)と共に、年1回の医師の診察と検査(マンモグラフィまたは超音波検査。2つを同時にすることで、さらに精度は上がります)を受けることをおすすめします。
- どのように行うのですか?
-
- ①初めに上半身お脱ぎ頂ます。
- ②ベッドに横になっていただき、専用のゼリーを塗ります。
- ③超音波を出す探触子(プローブ)を、乳房に当て動かしながら断面を画像に映し出し撮影して検査します。
- 乳腺超音波検査の特徴は?
-
- ①痛みはまったくありません。
- ②手に触れない数ミリのしこりを見つけ出すことが出来ます。
- ③ 超音波を使用しているためX線のような被爆はありません。
- ④乳腺組織の発達している40歳未満の方には特に適した検査です。
※検査は女性の臨床検査技師が対応いたします。
医療被曝について
- 妊娠中にX線検査を受けた場合の危険(リスク)について教えてください。
-
X線の身体への影響はX線を受けた体の部位と線量に依存します。妊娠中の胎児への影響は胎児が直接X線を受けた場合のみ問題となります。胎児のリスクは胎児死亡(流産)、奇形児の発生、精神発達の遅延、小児がんの発生、出生児の遺伝的影響などがありますが、被ばく線量と胎児の月齢によっても影響は異なります。胎児の確定的影響のしきい値は約100mGyといわれています。
- 胃のX線検査を受けた後で妊娠がわかり、胎児への影響が心配です。
-
妊娠初期には本人も気づかないまま、X線検査を受けて腹部に被ばくしてしまうことがあります。その場合、おそらく受胎後2~6週の時期であると考えられます。この時期には主要器官の形成期であり、奇形発生の可能性が考えられますが、この検査による被ばく線量は4~10mGyと推定され、奇形発生のしきい値の1/10程度ですので、胎児への影響を心配する必要はありません。
- 放射線を被曝すると子どもに影響が残るでしょうか?(本人だけではなく、「夫が注腸検査などを受けた後に妊娠した場合、子どもへの影響が心配」という内容も考えられる。)
-
本人の被ばくがその子孫に与える影響を遺伝的影響といいます。ただし、遺伝的影響が起こる可能性があるのは生殖腺が被ばくした場合で、それ以外の場所(例えば胸部)を被ばくしても遺伝的影響は起こりません。つまり、男性、女性ともに、生殖腺に被ばくしないかぎり遺伝的影響を心配する必要はありません。また、染色体異常などの遺伝的影響では、もともと自然発生する確率もありますが、人による疫学調査では、放射線に被曝したことにより遺伝的影響が有意に増加したことは確認されておりません。
したがって、遺伝的影響を心配する必要はほとんどありません。また、X線検査を受けるメリットが遺伝的影響というデメリットよりも充分におおきいことを理解することが大切です。 - X線検査室の周りには、放射線が漏れていませんか?
-
X線検査室の周りは管理区域と呼ばれ管理されています。3カ月間で1.3mSv以下になるような対策がとられていて、装置を使い始める前に測定することや、6カ月に一度はその値を確かめなければならないことになっています。3カ月で1.3mSv以下という値は、3カ月間検査室の壁際でじっとしていても、胸部の写真を正面と側面の2枚撮った程度の被ばく量だということです。1.3mSvは規制値ですので、実際はもっと少なくなるよう設計されています。