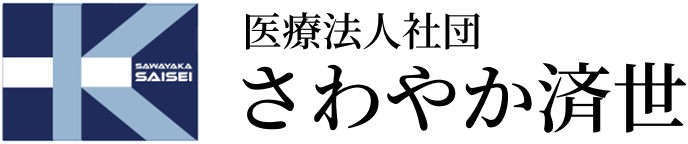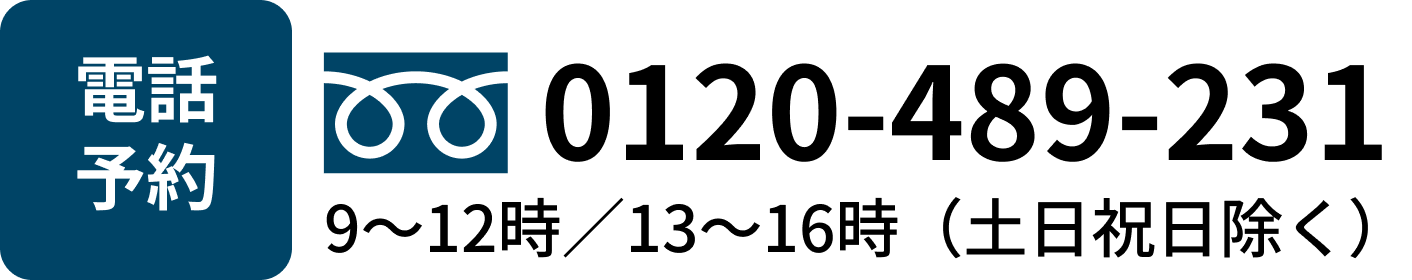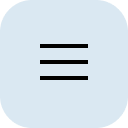よくお酒を飲むことから肝機能に不安を持っているという方は多いのではないでしょうか。よく知られているように、アルコールの大量摂取は肝臓に大きな負担を及ぼします。健康診断での肝機能検査では何を調べるのか、アルコールが原因の肝臓の病気にはどのようなものがあるか解説します。
健康診断で気にすべき肝臓の数値
健康診断や人間ドックには「肝機能検査」という項目があります。これは血液検査で血中の酵素の数値を測定するものですが、ALT、AST、γ-GTPなどアルファベットで書かれているので何のことなのか分かりづらいと感じる方も多いでしょう。これらの数値はいったいなにを現すものなのでしょうか?
AST(GOT)
こちらもALT(GPT)と似た働きをする酵素です。ただし、AST(GOT)は肝臓以外の心臓や骨格筋、赤血球などにも存在します。そのため、ALT(GPT)が正常値で、AST(GOT)値のみ高いときは、肝臓以外に異常が起きている可能性が高くなります。
ALT(GPT)
肝細胞に多く存在する酵素です。体内の栄養素をアミノ酸に変換して、エネルギー代謝の過程で重要な働きをします。何らかの異常があると肝細胞が傷つき血液中に漏れ出すため、その数値が高いと肝臓に障害が発生していると考えられます。
γ-GTP
肝臓、腎臓などで作られる酵素で、ALTとASTと同じくエネルギーの代謝を促しています。主に肝細胞や腎臓で働いており、アルコールを大量に摂取したり、薬の服用、肥満の影響などによって大量に作られると血液中に漏れ出して数値が上がります。
ALP
肝臓、腎臓、骨などで作られる酵素です。肝臓では通常毛細胆管膜に多く存在するほか、胆汁にも含まれています。肝障害が起きて胆汁の流れが悪くなると数値が高くなります。特に胆石や胆のう炎によって胆汁の排出が妨げられると数値が変化します。
骨折後や骨に負担がかかった場合でも、上昇することがあります。
総ビリルビン
ビリルビンは、血液中で赤血球が破壊されるときにできる色素です。ビリルビンが血液中に漏れ出しているときは、肝硬変、胆管がん、胆石、胆のう炎などが疑われます。安静時でも軽度上昇することもあります。
お酒好きに見られる肝臓の病気
肝臓の病気がアルコールの飲み過ぎによって起こりやすいことはご存知のとおりです。具体的にどのような病気があるのかを見てみましょう。
脂肪肝
お酒の飲み過ぎでまず生じるのが脂肪肝です。脂肪肝は肝臓にコレステロールや中性脂肪が蓄積した状態で、いわば肝臓の肥満症です。食べ過ぎ、肥満、糖尿病によっても脂肪肝になることがあり、アルコールに原因がある脂肪肝はアルコール性脂肪肝とも呼ばれます。
アルコール性肝炎
アルコール摂取で脂肪肝がさらに進行すると、アルコール性肝炎になります。肝臓が炎症を起こし、腹痛、発熱、黄疸の症状が現れます。脂肪肝の状態からさらに大量飲酒を続けると、アルコール性肝炎になると言われます。
肝硬変
アルコールによる肝臓病が長期化すると肝硬変になります。肝臓は小さく硬くなり、肝臓の機能が徐々に失われていきます。
自覚症状
沈黙の臓器とも言われる肝臓は、肝硬変に至るまではほとんど自覚症状がありません。しかし、肝硬変が進行していくと、徐々に特徴的な症状が現れ始めます。具体的には全身の倦怠感、食欲不振、発熱や微熱、手のひらが赤くなる、尿の色が濃くなる、むくみが見られる……などです。
皮膚や目の白目部分が黄色く変色する「黄疸」も起こります。黄疸は血液中のビリルビン濃度が異常に高くなることで現れます。
お酒をよく飲み、肝臓に不安のある方は、まず肝機能検査を受けてみましょう。ただし、数値結果や症状については自分で判断せず、医師に相談することが大切です。お酒が原因の肝障害は初期・中期であればアルコールを断つことで改善する可能性が高いので、医師の指導のもとで治療に専念するようにしましょう。